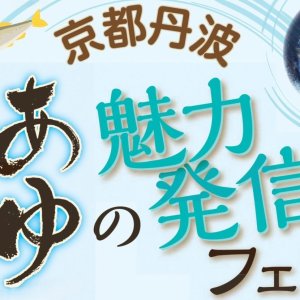ナイトファーム♪ライトアップされた畑で京野菜収穫体験(BNRファーム)西京
大好評のナイトファームは今年の夏も実施♪★毎日放送(MBS)よんチャンTV「最旬!丼マン」で紹介(2024年)★読売テレビ「かんさい情報ネットten.」で紹介(2024年)京都市西京区にあるBNRファームでは、野菜農家で日本初、全国唯一で初の試み(※)である「ナイトファーム~ライトアップされた畑で京野菜収穫体験~」を開催しています。夜の帳が降り静けさが訪れた頃、イルミネーションが灯るロマンチックな雰囲気の畑で京野菜の収穫体験を楽しんでいただけます。昨年、多くのメディアで取り上げられ、殆どの実施日が満席となる人気ぶり。今年は開催日、席数、期間も大幅に増やし、盤石の受け入れ態勢で臨みます。開催日は、2025年7月1日(火)~11月9日(日)の木曜日を除く毎日実施。スタンダードコースに加え、内容充実の「プレミアムコース」を追加しました。さらに、BNRオリジナル企画「キャンドルすくい」、「線香花火」といった夏らしい体験に加え、農園ならではの夏のドリンク「スイカサイダー」の提供など、日本の夏を感じられる催しを日替わりで実施します。また、秋の催しも絶賛企画中です。今まで味わったことのない、特別な夏から秋の夜の経験を是非お楽しみください。ご家族、カップル、ご友人お誘いあわせの上、ご予約お待ちしております。おひとり様参加も大歓迎です。ご予約、開催内容・日時の詳細は下記の①・②いずれかでご確認ください。なお、料金(スタンダードコース)は、公式サイトからの予約が割安でお得です。①BNRファーム公式サイト②じゃらん※BNRファームが独自に調査した限り、野菜農家としては業界初となる試み<ナイトファーム概要ナイトファームは京都の農家集団「BNRファーム」が主催する、ライトアップされた畑で京野菜収穫体験する夜間の農業体験イベントです。約1,000球のイルミネーションが灯る畑を舞台に、京野菜の収穫体験や石窯でのピザ作り、野菜を使ったディナーなどをお楽しみいただけます。夜の帳が降りる頃、ライトアップされた幻想的な畑にて有機肥料を使い、手間暇かけた栽培を行なった、旨味や甘味たっぷり自慢の京野菜をはじめとした夏野菜を収穫ください。収穫できる野菜は最大約20種類。京の伝統野菜の賀茂茄子、万願寺とうがらしをはじめ、キュウリ、ピーマン、枝豆など、旬の夏野菜です。収穫時、採れたての野菜をまずは生の状態で野菜本来の味を確かめてください。その場でお召し上がりいただくことにより、農業の魅力や自然の美しさ、野菜の素晴らしさを五感で感じていただけます。収穫後、採れたての夏野菜を炭火焼、ピザで味わっていただきます。熱を加えることにより、一層野菜本来の甘味が引き立ちます。大人の方には、2,000円相当の夏野菜のお土産付。ご自宅でもBNRファーム自慢の野菜を存分にご堪能ください。ナイトファーム詳細 ■開催日時:2025年7月1日(火)~11月9日(日)の木曜日を除く毎日開催■開催時間(2部制)・プレミアコース:①18:00~20:30、②19:00~21:30・スタンダードコース:①18:00~20:00、②19:00~21:00■開催場所:BNRファーム農園(京都市西京区大原野上里南ノ町736)※ナイトファームはペットも同伴可能■開催内容・プレミアコース農家がマンツーマンで接客を行う、より丁寧な体験コース。ピザのトッピングやドリンクなどのオプションがすべて含まれたオールインクルーシブ。収穫体験では、野菜の豆知識や育て方など、農家から直接話を聞きながら体験できます。・スタンダードコースしおりを見ながら、各体験を自由に進めるセルフ形式のコース。収穫からピザ作りまで、自分のペースで気軽にお楽しみいただけます。■体験内容・収穫体験(収穫できる野菜は時期により異なります)ライトアップされた夜の畑で、京野菜の収穫体験ができます。収穫できる野菜は最大約20種類。(一例)千両なす、賀茂なす、水なす、長なす、緑なす、白なす、小なす、きゅうり、オクラ、アイコ、プチトマト(黄・薄ピンク)、万願寺とうがらし、ピーマン、パプリカ、ししとう、鷹の爪、ポブラノ、ズッキーニ、まくわうり、枝豆 など。・ピザ作り体験収穫した野菜を使って、自分で具材をカットし、石窯で焼き上げるピザ作りを体験できます。プレミアムコースは、お肉系・魚介系などのトッピングやドリンク付き。スタンダードコースは、オプションでお肉系・魚介系などのトッピングやドリンクの追加注文も可能です。・ディナー(野菜料理)手作りピザに加え、収穫したての野菜を使った農家直伝の一品料理をご提供。(一例)万願寺とうがらしのBBQ、オクラのオイル焼き、極ウマ茄子など・お持ち帰り野菜(約2,000円相当)体験で収穫した京野菜はそのまま指定袋に詰め放題し、お持ち帰りいただけます。ご自宅でも余韻を楽しめます。■料金(税込)・プレミアコース公式サイト・じゃらんからの予約(共通):大人(中学生以上)13,200円、小学生6,600円・スタンダードコース公式サイトからの予約:大人(中学生以上)5,500円、小学生2,750円じゃらんからの予約:大人(中学生以上)6,600円、小学生3,300円※いずれもコースも小学生未満は無料※大人の方には、2,000円相当の野菜のお土産付(小学生の方には野菜のお土産は付きません)■ご案内・汚れても気にならない、動きやすい服装でお越しください。お子さまは長靴のご持参をよろしくお願いいたします。・夏季期間は、夜でも熱中症の可能性があります。こまめな水分・塩分補給を心がけてください。BNRファームとはBNRとは、2020年に京都・大原野で新規就農した30・40代のメンバーで構成される農業グループです。上田農園・塔伊農園の監修もと、約20種類の多品種の露地栽培の野菜を甘味や旨味を向上させる為に様々な技術を駆使して栽培しています。また、収穫体験や農業体験の提供などの農業振興、全国の児童養護施設や子ども食堂への野菜の寄附、フードロス削減と地域活性化など多岐にわたる事業を展開しています。さらに、農作業のLive配信等、SNSを通じた情報発信や農業体験の提供等を通じて、年々担い手が減る農業の素晴らしさを社会に伝えると共に、食と農業の課題解決に日々邁進しています。新規事業である、夜の野菜収穫体験「ナイトファーム」では、畑をライトアップし非日常感を演出した雰囲気の中、その時期にしか味わえない旬の京野菜の収穫体験などのサービスを提供しています。ナイトファーム以外にも、お昼間の野菜収穫体験や竹の子掘り体験、本格的な農家体験プランなど年間を通じ様々な農業体験プログラムを実施しています。また、子供向けマラソン大会、プロギング(ゴミ拾いとジョギングを掛け合わせたスウェーデン発祥のSDGsフィットネス)など、農業以外にも様々な社会貢献イベントを数多く実施しています。■BNRファーム代表理事:寺島 美羽(てらしま みう)2001年生まれ。立命館大学国際関係学部卒業。高校時代より、気候変動問題に取り組む若者のムーブメント「FFF Kyoto」の代表を務める。令和3年度京都市環境審議会・地球温暖化対策推進委員会の委員や、京都市が推進する「京都発脱炭素ライフスタイル 2050京創ミーティング」のチームメンバーとしても活動。大学在学中は、有機農家や農を中心とした体験型事業の現場を全国各地で巡りながら実践を重ね、2024年よりBNRファームで本格的に活動を開始。翌年、一般社団法人BNRを設立。気候変動による収穫量の不安定化や、担い手不足といった広範な課題が深刻化する中、農業を取り巻く問題に多面的にアプローチし、持続可能な未来に向けた取り組みを行っています。(情報提供:BNRファーム)エリア名西京イベント名ライトアップされた畑で京野菜収穫体験開催日時2025年7月1日(火)~11月9日(日) の木曜日を除く毎日・プレミアコース:①18:00~20:30、②19:00~21:30・スタンダードコース:①18:00~20:00、②19:00~21:00開催場所BNRファーム農園所在地京都市西京区大原野上里南ノ町736料金・プレミアコース:公式サイト・じゃらんからの予約(共通):大人(中学生以上)13,200円、小学生6,600円・スタンダードコース:公式サイトからの予約:大人(中学生以上)5,500円、小学生2,750円、じゃらんからの予約:大人(中学生以上)6,600円、小学生3,300円※いずれもコースも小学生未満は無料予約(公式サイト)https://bnr-kyoto.deca.jp/予約(じゃらん)https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000217007/アクセスJR京都線向日町駅または阪急京都線東向日駅から、阪急バス64系統右京の里(循環) 乗車、紅葉町下車徒歩10分、阪急バス63系統洛西バスターミナル行乗車、右京の里下車徒歩11分JR京都線桂川駅または阪急洛西口駅から京都市バス西9系統乗車、紅葉町下車徒歩10分阪急東向日駅からタクシーで約10分(1,200円程度)URLhttps://bnr-kyoto.com/Instagramhttps://www.instagram.com/bnr1111_kyoto/ ...